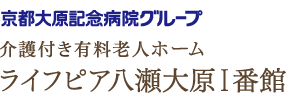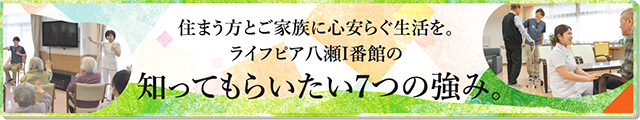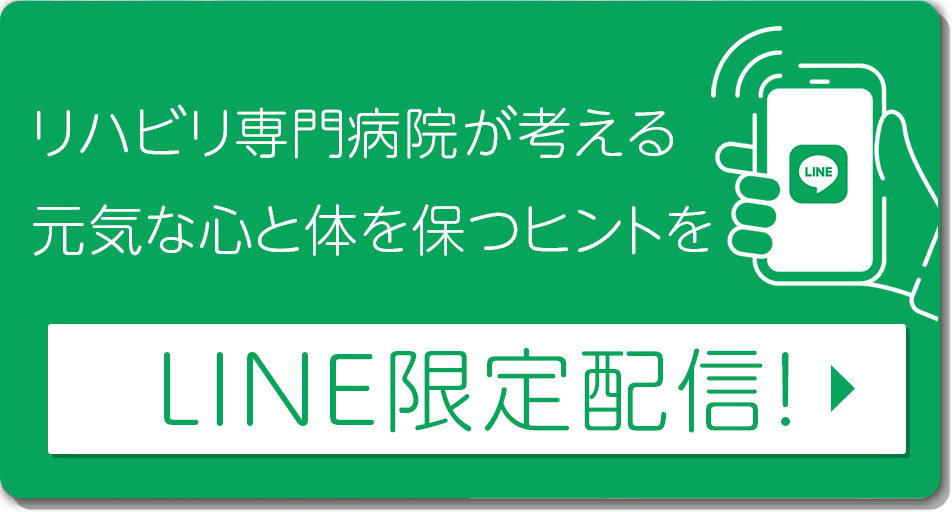介護保険が適用される特定疾病とは?対象となる16種類をご紹介
こんにちは、介護付き有料老人ホーム ライフピア八瀬大原Ⅰ番館です!
みなさんは介護保険について「介護が必要な高齢者が申請できるもの」と思っていませんか?
原則的として介護保険は、介護が必要な65歳以上の高齢者に適用されます。
ただし「特定疾病」とよばれる病気・症状に該当する方は、65歳未満でも介護保険が適用されます。
今回は介護保険の対象となる「特定疾病」について、詳しく見ていきましょう。

そもそも介護保険や特定疾病とは?介護保険の主な対象者は?
まずは介護保険について、対象者の区分などを見ていきましょう。
また、特定疾病についても解説します。
介護保険とは?
介護保険とは一定の条件下で自治体から要介護認定を受けた場合、介護サービスの利用ができる制度のことです。
40歳になると被保険者として介護保険に加入します。
高齢化が進む中で介護を受ける人も増え、このような人たちを社会全体で支えていくための制度として始まりました。
介護保険制度のサービス対象者は、次の2区分があります。
- ①第一号被保険者:65歳以上の高齢者で介護を必要とする人
- ②第二号被保険者:40歳~64歳で医療保険に加入しており、特定疾病により介護を必要とする人
65歳以上の人しか利用できないと思われがちな介護保険ですが、「特定疾病」の症状がある人であれば、②の第二号被保険者として40歳から利用できます。
では、「特定疾病」とはどのようなものでしょうか?
特定疾病とは?
厚生労働省によると特定疾病とは、「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病」と説明されています。
(参考:厚生労働省ホームページ)
なんだか難しいですね。
具体的には、次の①と②の条件を満たす疾病を特定疾病と呼びます。
①65歳以上の高齢者に多く発生している疾病。
また、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められるなど、加齢と関係があって発症すると医学的に定義できる病気。
②3~6ヶ月以上継続して要介護状態または要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。
①、②の条件を満たし「要介護認定」を受けると、40歳以上65歳未満の人でも第二号被保険者として介護サービスが利用できます。
ただし、①の内容にもある通り「加齢との関係が認められる疾病」が条件なので、介護が必要であっても交通事故などが原因となる場合は認定されません。
2021年現在、特定疾病は16種と定められています。
介護保険の対象となる特定疾病16種

実際に次の16種の疾病にかかり介護が必要となる場合、64歳以下でも介護保険の対象となります。
1 がん(がん末期)
医師が一般に認められている医学的知見に基づき、治癒が困難で回復の見込みがない状態(余命6か月程度)に至ったと判断した末期のものに限ります。
2 関節リウマチ
関節が炎症を起こして軟骨や骨の機能が失われ、関節が機能しなくなる症状です。
放置すると関節の変形を起こします。
関節を動かさなくても、関節の腫れや激しい痛みがあるのが特徴です。
3 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
筋萎縮性側索硬化症(ALS)は、手足・のど・舌の筋肉や呼吸に必要な筋肉が徐々にやせ、力が入らなくなる疾病です。
筋肉そのものの病気ではなく、筋肉を動かす指令を出す脳の神経に障害を受けることで起こります。
いまだに治療方法は確立されていません。
4 後縦靱帯骨化症(OPLL)
後縦靱帯骨化症(OPLL)は、背中を縦にはしる靱帯(後縦靱帯)が骨になってしまうことで脊髄が入っている脊柱管が圧迫され、感覚障害や運動障害を引き起こす疾病です。
5 骨折を伴う骨粗鬆症
骨粗鬆症(こつそしょうしょう)は骨密度の低下で骨がもろくなること。
通常、骨折は強い力が骨にかかることで起こりますが、この状態にあると日常生活の中の軽度の負担でも骨折が起きやすくなります。
骨粗鬆症は椎体骨折(背骨・脊椎)を伴うものが特定疾患として認められます。
6 初老期における認知症
認知症は高齢者だけではなく若年層でも発症することがあります。
厚生労働省の基準では40~64歳で発症した場合、特定疾病としてみなします。
40~65歳で発症する認知症の代表的なものは下記の3つです。
初期症状がもの忘れから始まる「アルツハイマー型認知症」では、進行すると整理整頓ができなくなり意欲の低下が見られます。
「脳血管性認知症」は、もの忘れだけでなく歩行障害や排尿障害も症状として現れます。
頭部画像検査をすると、認知症をひきおこす部位に脳血管障害が発見されます。
「レビー小体認知症」は幻視体験などが特徴的な疾患です。
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
脳の細胞が衰弱して筋肉のこわばりや歩行障害などが起こる「パーキンソン病」と、パーキンソン病と同様の症状を伴う「進行性核上性麻痺」「大脳皮質基底核変性症」。
この3つの疾患の総称が「パーキンソン病関連疾患」です。
進行性核上性麻痺とは、脳の一部の神経細胞が減少し、転びやすい、下が見にくい、しゃべりにくい、飲み込みにくいといった症状があらわれる病気のことです。
大脳皮質基底核変性症は、パーキンソン症状と大脳皮質症状(手が意思どおりに動かない、動作のぎこちなさなど)が同時にみられる症状です。
パーキンソン病では、震え、動作ののろさ、筋肉のこわばり、転びやすいといった症状が見られます。
8 脊髄小脳変性症
脊髄小脳変性症では、小脳の一部に障害を受け、歩行時のふらつき、手の震え、ろれつが回らないといった運動症状が見られます。
9 脊柱管狭窄症
脊柱管狭窄症は、脊髄の神経が通る脊柱管が圧迫され、神経の血流が低下することです。
歩くことで臀部(でんぶ)や下肢に痛みが生じ、長時間の歩行が困難になります。
一定時間休息をとることで歩行の継続ができる状態です。
10 早老症
早老症は、老化の兆候が実際の年齢よりも早く起こる疾病です。
早老症には約10の疾患があり、プロジェリア症候群やウェルナー症候群などが当てはまります。
11 多系統萎縮症
多系統萎縮症の症状は、発病当初はパーキンソン病に似ています。
のちに体のふらつきや排尿障害などが出現し、抗パーキンソン病薬も効果が無くなってしまいます。
多系統萎縮症は大きくシャイ・ドレーガー症候群、線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症の3つに分類されます。
12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
糖尿病自体は特定疾病として認められませんが、糖尿病が原因の下記の合併症は特定疾病となります。
糖尿病性神経障害は、糖尿病性神経障害糖尿病にかかり高血糖になることで、末梢神経が壊され、感覚・運動・自律神経に障害を及ぼす疾病です。
糖尿病性腎症は糖尿病性腎症糖尿病により高血糖の状態が続くことで動脈硬化が進行、高血圧・腎臓機能の低下を引き起こします。
糖尿病性網膜症は、糖尿病性網膜症尿病により、目の中の網膜組織が障害を受け、視力が低下する症状です。
13 脳血管疾患
脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、一過性脳虚血発作などが脳血管疾患に当てはまります。
死亡率が高い疾患で、一命を取りとめても後遺症が残ることが多いです。
14 閉塞性動脈硬化症
閉塞性動脈硬化症は、手足の動脈硬化が起こり、血管が狭くなったり血管が詰まったりする症状です。
血流が悪くなることで手足に送る酸素や栄養が不足し、手足の痛みや歩行障害などさまざまな障害が出ます。
15 慢性閉塞性肺疾患
慢性閉塞性肺疾患は喫煙を主原因とする肺の炎症性疾患です。
慢性気管支炎や肺気腫、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎などによって、体を動かしたときに息切れや動悸を起こしたり、慢性の咳や痰(たん)が出たりします。
16 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
両膝の関節や股関節が変形を起こし、痛みが生じたり、可動域が狭くなったりする場合に特定疾病として認められます。
介護保険の対象となる特定疾病にあてはまる方は自治体に相談を
65歳以上の高齢者のためのものだと思われがちな介護保険ですが、40歳~64歳の人でも老化に基づき発症した特定疾病と診断されれば介護サービスを受けることができます。
国が認める特定疾病は16種。
いずれかにあてはまる方は、自治体に相談してみましょう。
ライフピア八瀬大原Ⅰ番館のコラムでは、高齢者の安心な暮らしや住まいに役立つお役立ち情報を随時発信しております。
お悩みや疑問があれば、ぜひ参考にしてみてくださいね。
この記事を監修した人

- 星野 英俊 (ライフピア八瀬大原Ⅰ番館 事務長)
- 京都大原記念病院グループに介護職として新卒入職。京都大原記念病院 現場介護スタッフ、介護老人保健施設で施設相談員(ケアマネジャー)などとして約15年間、現場業務に従事。
事務職 転身後、ライフピア八瀬大原Ⅰ番館の事務長に就任し、
現在に至る。